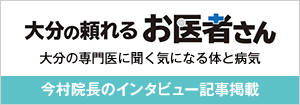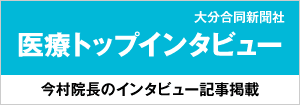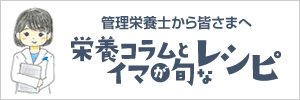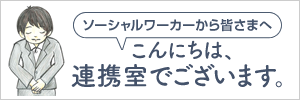管理栄養士コラム
【第3回】秋こそ¨脱¨早食い
2019-10-16

早食いはなぜ悪いの?
脳が腹と感じるには時間がかかります。早食いの人は満腹と感じるよりも
先に次々と食事をしてしまうため、食べるのが多くなってしまう傾向に。
体が本来必要としている以上の量を食べてしまうため、体重増加や
血糖値の上昇、やがては肥満や糖尿病などの生活習慣病になる危険性も
高まっていきます。健康な体を維持するためにも注意しましょう。
☆ゆっくり食べることは体に好影響☆
・脳の働きを活性化~認知症予防
・エネルギーを消費~肥満予防
・味覚の活性化~唾液の分泌促進
・歯の病気を防ぐ~虫歯や歯周病予防
・胃腸の働きを促進~消化吸収を促す
☆“脱”早食いのポイントは『よく噛む』☆
~目標はひと口30回以上~
~15分以上かけて食べる~
脳から分泌される食欲を抑制するホルモンが「レプチン」で、このホルモンが
多く分泌されるのは食後20分後。時間をかけながら食事することは「レプチン」
を多く分泌し、満腹感を得るためにも大切です。
☆噛む回数を増やす工夫☆
工夫1:歯ごたえのある食材を選ぶ→根菜類、キノコ類、こんにゃく類、海藻など
工夫2:食材を大きく厚めに切る→飲み込むまでに自然と噛む必要があるため
工夫3:茹で時間は短めにする→少し堅めの食感が残ることで噛む回数を増やす
工夫4:飲み物を飲みすぎない→噛む回数が減ってしまわないように
工夫5:人と一緒に食べる→会話を楽しみながらゆっくりと食べる
工夫6:ながら食いはしない→食事に集中して、しっかりと噛むことを意識する
脳が腹と感じるには時間がかかります。早食いの人は満腹と感じるよりも
先に次々と食事をしてしまうため、食べるのが多くなってしまう傾向に。
体が本来必要としている以上の量を食べてしまうため、体重増加や
血糖値の上昇、やがては肥満や糖尿病などの生活習慣病になる危険性も
高まっていきます。健康な体を維持するためにも注意しましょう。
☆ゆっくり食べることは体に好影響☆
・脳の働きを活性化~認知症予防
・エネルギーを消費~肥満予防
・味覚の活性化~唾液の分泌促進
・歯の病気を防ぐ~虫歯や歯周病予防
・胃腸の働きを促進~消化吸収を促す
☆“脱”早食いのポイントは『よく噛む』☆
~目標はひと口30回以上~
~15分以上かけて食べる~
脳から分泌される食欲を抑制するホルモンが「レプチン」で、このホルモンが
多く分泌されるのは食後20分後。時間をかけながら食事することは「レプチン」
を多く分泌し、満腹感を得るためにも大切です。
☆噛む回数を増やす工夫☆
工夫1:歯ごたえのある食材を選ぶ→根菜類、キノコ類、こんにゃく類、海藻など
工夫2:食材を大きく厚めに切る→飲み込むまでに自然と噛む必要があるため
工夫3:茹で時間は短めにする→少し堅めの食感が残ることで噛む回数を増やす
工夫4:飲み物を飲みすぎない→噛む回数が減ってしまわないように
工夫5:人と一緒に食べる→会話を楽しみながらゆっくりと食べる
工夫6:ながら食いはしない→食事に集中して、しっかりと噛むことを意識する
☆噛み噛みメニュー
鶏肉とキノコの重ね蒸し (2人分)
[材料]
・鶏肉ももひと口カット 150g
・塩、こしょう 少々
・酒 小さじ1
・糸こんにゃく 50g
・しめじ 1/2株
・しいたけ 2枚
・ポン酢 大さじ3
・ごま油 大さじ1
[作り方]
・鶏肉に下味を付ける。糸こんにゃくは下茹でする。
・しめじは石づきを取り、ばらす。シイタケはスライスにする。
・浅めの皿に割り箸を格子状に並べ、その上にクッキングシートをのせ、
竹串で2~3か所穴をあける。
・皿に糸こん、しめじ、しいたけを等分に盛り、上に鶏肉をのせる。
・ラップをかけて、電子レンジで(600W)で5~6分ほど加熱する。
・鶏肉に火が通ったら、ポン酢とごま油をかける。
[材料]
・鶏肉ももひと口カット 150g
・塩、こしょう 少々
・酒 小さじ1
・糸こんにゃく 50g
・しめじ 1/2株
・しいたけ 2枚
・ポン酢 大さじ3
・ごま油 大さじ1
[作り方]
・鶏肉に下味を付ける。糸こんにゃくは下茹でする。
・しめじは石づきを取り、ばらす。シイタケはスライスにする。
・浅めの皿に割り箸を格子状に並べ、その上にクッキングシートをのせ、
竹串で2~3か所穴をあける。
・皿に糸こん、しめじ、しいたけを等分に盛り、上に鶏肉をのせる。
・ラップをかけて、電子レンジで(600W)で5~6分ほど加熱する。
・鶏肉に火が通ったら、ポン酢とごま油をかける。