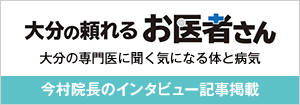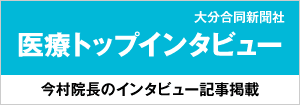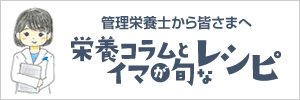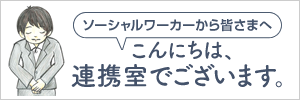管理栄養士コラム
【第16回】糖化は血管の焦げ⁉高血糖を防ごう!その②
2020-10-16

体に悪影響を及ぼす二大老化原因は【酸化】と【糖化】と言われており、最近では
【糖化】に注目されています。【糖化】とは体内にある余分な糖質がたんぱく質と結び
つくことで老化物質が発生します。これをAGEs(終末糖化産物)と呼びます。AGEsが
蓄積されると動脈硬化・皮膚の老化・認知症・糖尿病の合併症・骨粗しょう症などが
引き起こる原因になります。【糖化】は体内の余分な糖質が原因となり、糖質の過剰摂取が続くと高血糖を招きます。【糖化】を阻止するためには血糖値が上がりにくい食材を選ぶこと、食事の最初に食物繊維を摂るなどして、血糖値の急上昇を防ぐこと、また【糖化】を防ぐ食材を上手く取り入れることが大切です。
【糖化】に注目されています。【糖化】とは体内にある余分な糖質がたんぱく質と結び
つくことで老化物質が発生します。これをAGEs(終末糖化産物)と呼びます。AGEsが
蓄積されると動脈硬化・皮膚の老化・認知症・糖尿病の合併症・骨粗しょう症などが
引き起こる原因になります。【糖化】は体内の余分な糖質が原因となり、糖質の過剰摂取が続くと高血糖を招きます。【糖化】を阻止するためには血糖値が上がりにくい食材を選ぶこと、食事の最初に食物繊維を摂るなどして、血糖値の急上昇を防ぐこと、また【糖化】を防ぐ食材を上手く取り入れることが大切です。
糖化を阻止する力の強い食材
糖化を防ぐ食品② ☆こんにゃく☆
こんにゃくに含まれるグルコマンナンは水溶性の食物繊維の一種です。水溶性の食物繊維は食後血糖値の上昇を抑えるほかにも血中の悪玉コレステロールの低下や腸内の善玉菌を
増やして腸内環境を整えるなどの働きがあります。食物繊維は腸での糖の吸収を緩やかに
してくれるので高血糖状態を防ぐためには毎日取り入れたい食材です。
ただし、過剰に摂取するとお腹がゆるくなる場合があるので適量を守りましょう。
適量は1日250g程度(板こんにゃく1枚分)
糖化を防ぐ食品② ☆こんにゃく☆
こんにゃくに含まれるグルコマンナンは水溶性の食物繊維の一種です。水溶性の食物繊維は食後血糖値の上昇を抑えるほかにも血中の悪玉コレステロールの低下や腸内の善玉菌を
増やして腸内環境を整えるなどの働きがあります。食物繊維は腸での糖の吸収を緩やかに
してくれるので高血糖状態を防ぐためには毎日取り入れたい食材です。
ただし、過剰に摂取するとお腹がゆるくなる場合があるので適量を守りましょう。
適量は1日250g程度(板こんにゃく1枚分)
✿ヘルシー!こんにゃくメニュー✿
糸こんのお手軽チャプチェ
【材料(2人分)】
・糸こんにゃく(白滝) 1袋(200g)
・牛肉(小間切れ) 150g
・玉ねぎ 1/2玉
・にんじん 40g
・ピーマン 中2個
・ごま油(サラダ油) 小さじ1
・鶏がらスープの素(顆粒)小さじ1
・料理酒 大さじ1
・焼き肉のタレ 大さじ1・1/2
・すりごま 小さじ1
糸こんのお手軽チャプチェ
【材料(2人分)】
・糸こんにゃく(白滝) 1袋(200g)
・牛肉(小間切れ) 150g
・玉ねぎ 1/2玉
・にんじん 40g
・ピーマン 中2個
・ごま油(サラダ油) 小さじ1
・鶏がらスープの素(顆粒)小さじ1
・料理酒 大さじ1
・焼き肉のタレ 大さじ1・1/2
・すりごま 小さじ1
【作り方】
①白滝を水洗いし、よく水気を切っておく。
②玉ねぎは薄くスライスにし、にんじん・ピーマンは千切りにする。
③フライパンにごま油を入れ、白滝と切った野菜と鶏がらスープの素を
入れて中火で炒める。
④野菜が軽くしんなりしたら、牛小間肉と料理酒を入れてさらに炒める。
⑤牛小間肉に火ったら、焼肉のタレを回しかけてさっと炒め、お皿に盛る。
⑥上からすりごまをかけて出来上がり。
①白滝を水洗いし、よく水気を切っておく。
②玉ねぎは薄くスライスにし、にんじん・ピーマンは千切りにする。
③フライパンにごま油を入れ、白滝と切った野菜と鶏がらスープの素を
入れて中火で炒める。
④野菜が軽くしんなりしたら、牛小間肉と料理酒を入れてさらに炒める。
⑤牛小間肉に火ったら、焼肉のタレを回しかけてさっと炒め、お皿に盛る。
⑥上からすりごまをかけて出来上がり。